榊原寛/畳部屋さんが開発を進めている『歴史の終わり』は、架空の中世を舞台としたサンドボックス型戦略RPGです。プレイヤーはNPCと交流することによって、一度きりのストーリーをその都度ゲームのなかに立ち上げることができます。最終面談ではキャラクターと背景のイラストについてまず報告がなされ、タイトル名やロゴのデザインに関して意見交換がなされました。また、成果発表イベントでどのようにゲーム関係者にアピールするのかというトピックついてもアドバイザーと戦略が練られました。
アドバイザー:さやわか(批評家/マンガ原作者)/原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)
最終面談:2025年1月21日(火)
完成度のさらなる向上を目指して、できること
イラストと背景の進捗について
初回面談時に課題としてあげられていた、キャラクターと背景の進捗について榊原さんから話されます。「キャラクターと背景のイラスト制作は順調に進んでいて、1月末までに主要な素材が納品予定です。キャラクターは雌鹿さん、斉藤ミヤビさんにそれぞれ担当してもらっているのですが、若干彩度が異なるので納品後キャラと背景が合うように調整します。予算内で発注ができ、かつ大量の絵を画力のあるイラストレーターにお願いでき本当に良かった」と話します。続いて、3人体制で行われたテストプレイのフィードバックについても共有が行われました。「プレイヤーがNPCキャラクターの人生を観察し、それぞれの物語を長期的に想像できる点が好評で、そこは意図通りでした。一方でゲーム開始直後に敗北するケースもあり、ランダムにストーリーが生成してしまうため調整が必要だなと感じました。UIも分かりづらいという指摘があったため、引き続きブラッシュアップしていきます」。

ここでアドバイザーの原久子さんは、テストプレイについて全員がこうしたシュミレーションゲームに親しんでいる人だと複数人で行う意味が薄れると指摘します。榊原さんはこういったタイプのゲームをあまり遊ばない方にもお願いしたと応じ配慮したことを報告しました。

次に開発進行中のゲームが、榊原さんのテストプレイによってプレゼンテーションされ、話題は成果発表イベントでのインストールについて展開していきます。「実際のプレイは『信長の野望』にも似ています。町にいるといろんな人が動いていて、そのなかでプレイヤーは動いていきます。ランダムイベントが起きたり、酒場などでNPCと交流することができます。地図を見ると、関係性のあるキャラクターがどこにいるのかも分かります。成果発表では試遊をしてもらいつつ、1分くらいのトレーラーをつくって、ループにして流す予定なのですが、『スーパーマリオ』のように1、2分遊んでも面白くないので、トレーラーでは派手な戦闘シーンを見せたいと考えています」。

タイトルやロゴデザインをどうするか
「歴史の終わり」というタイトルは、フランシス・フクヤマの同名の著作から取られたものです。それに関連し榊原さんから「タイトルの『歴史の終わり』を検索しても本についてばかりが出てくるんです。それが作品名としていいのか悪いのかということと、また基本的なこととして商標にかぶってないのかも不安」と懸念が表明されました。
それに対してアドバイザーのさやわかさんは「まず権利のご懸念は、『歴史の終わり』という言葉自体はしばしば使われる一般的なものなので問題ないと思います。作品名としての良し悪しに関しては、英語圏の人はタイトルにあまり凝らない印象があるので、これも問題ないかなと思います」と述べ、次のように続けます。「オリジナリティを出すためによくある方法はサブタイトルを付けることでしょうか。それ以外にも、タイトルやSteam用のロゴをちゃんとつくることも重要です。例えば『ファイナルファンタジーⅦ』は、隕石というタイトルを象徴するようなワンポイントが入っていて、デザインされていますね」。
現状では、予算をイラストレーターに支払うために割いたため、ロゴやUI、音楽についてはフリー素材や仮の画像生成AIによるものが残ったままになっています。今後の対応については検討中です。
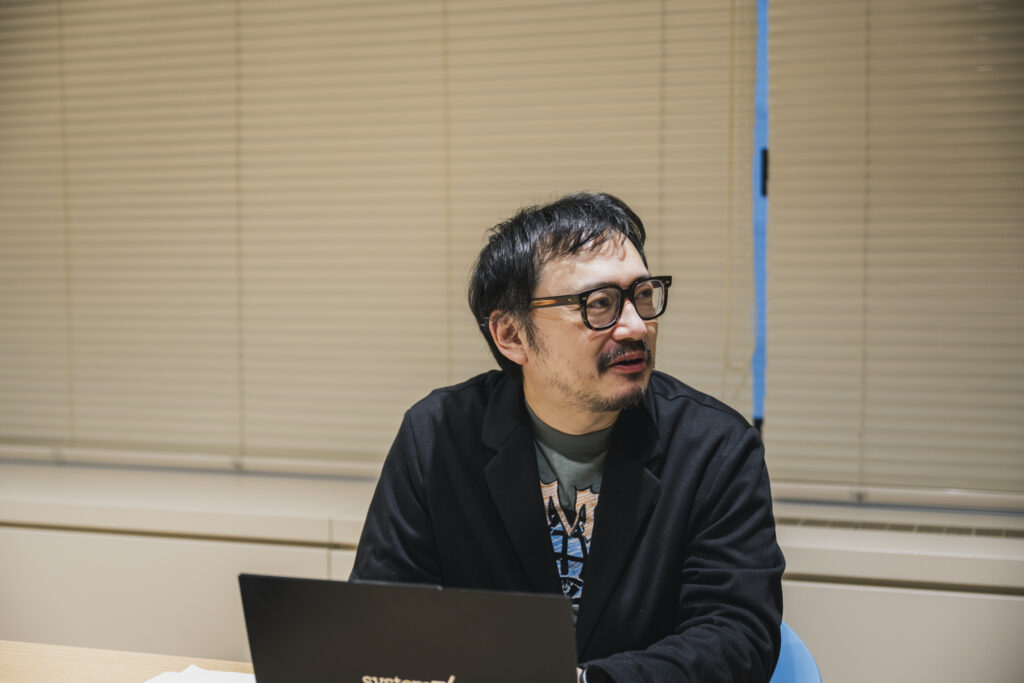
対外的なアピールを
このように足りない予算を補填するためにも、榊原さんは成果発表イベントを重要なアピールの場としたいと考えており、「展示にゲーム業界の方にも来ていただいて、パブリッシャーさんにサポートをいただけるみたいな契約につなげたい」と述べます。関係者へのプレスリリースや、情報周知には事務局のサポートも得られます。
現状翻訳は英語のみであることについて、さやわかさんからはインディーゲームの広報担当者から聞いてこととして、最近は英語に加え中国語も必須の指摘があるなど、ローカライズも含めた完成に向け建設的なアドバイスが送られました。
TO BE CONTINUED…
イラストの調整、UIのブラッシュアップ、トレーラーの編集を行い、パブリッシャー契約につなげていく

