2022年の設立以来、4つのゲームを制作してきたインディーゲームスタジオ・HIHAHEHO Studio。制作の中心的役割を担うmgr allergen0024さんは「人それぞれ異なる知覚や感情を通じて世界を捉えている中で、安易に他者を否定することに問題意識を持つ」と言い、その問題意識が作品のコンセプトにつながっています。『swandive』は、立場の違いが生む「多様な真実」を複数の視点で描く4章構成のノベルゲームです。初回面談では1章のストーリー構成についてアドバイザーと議論を交わしながら、今作のビジュアル面の特徴である「複数ウインドウ」の可能性を探っていきました。
アドバイザー:米光一成(ゲーム作家)/西川美穂子(東京都美術館学芸員)
初回面談:2025年9月18日(木)
複数ウィンドウを生かした演出を考える
キャラクターの視点とプレーヤーの体験のシンクロを狙う
身近に統合失調症の人がいることや自身の感覚過敏などを背景に、健常者の見え方のみが正解ではないということを問題意識として制作に取り組んでいるHIHAHEHO Studioのmgr allergen0024さん。今回採択された企画『swandive』は、事件を複数の立場から追うノベルゲームで、複数の視点を表すため3つのウィンドウを同時に表示することが特徴です。現在は、ゲームに組み込むアニメーションの制作とUIの検討を進めています。


埼玉・秩父をモデル地とする1章は、神の山とも呼ばれる「武甲山」の採掘を巡る対立がテーマとなっています。反対運動の当事者や採掘現場で働く親を持つ子どもなど、立場の異なる3人のキャラクター「アサ」「ユウ」「ヨル」を登場させ、現代社会のリアリズムを描きたい、とmgr allergen0024さんは話しました。アサ視点のゲーム画面(試作)をデモンストレーションしながら、「3ウィンドウ表示を保ちつつUIをどのように洗練させていくかが課題だ」と伝えました。
アサ視点でプレイしている時に別のウィンドウでユウやヨルの視点を同時に表示することでキャラクターの動きを俯瞰したり、複数のウィンドウを連動させてキャラクター同士の会話を多視点で見せたりすることも検討していると言うmgr allergen0024さん。その話を受けて、アドバイザーの米光一成さんは参考作品として『ダレカレ』(講談社ゲームクリエイターズラボ、2025年)、『Sing a Song for Freddy』(HaoLiao、2022年)『Florence』(Mountains、2018年)、などを挙げました。画面の切り替わり方やキャラクター間の相互作用、プレーヤーの操作とキャラクターの感情をシンクロさせる仕組みなどを参考にしてみてはと伝えました。
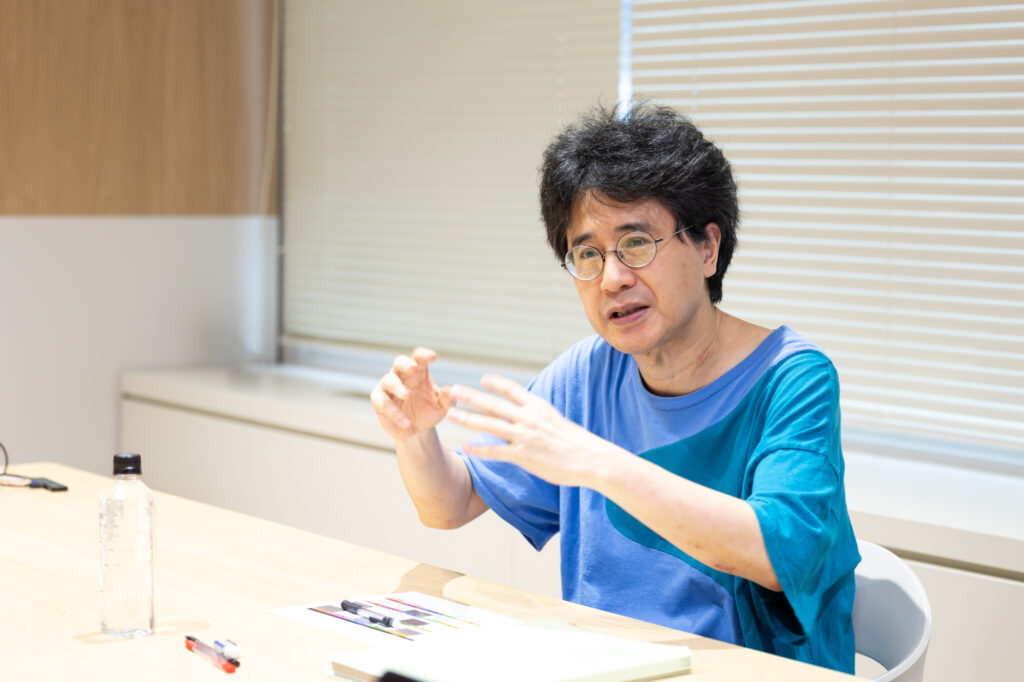
作品のテーマをどうビジュアルに落とし込むか
米光さんは、俯瞰を取り入れるとそれが“真実”になってしまいがちである点を指摘。作品のテーマに「多様な真実」を掲げながらも俯瞰を導入する意図を尋ねました。mgr allergen0024さんは、複数のウィンドウを用いることによる視覚的な楽しさを追求する中で、今は実験的に俯瞰を取り入れていると答えます。また、各キャラクター視点の会話が異なるなど、俯瞰が真実にならないあり方も考えています。
アドバイザーの西川美穂子さんからは、3つのウィンドウを効果的に使ってストーリー展開へとつなげていきたい中で、現状ではキャラクターの動きや展開が予測できてしまうため魅力が弱いのではないかと指摘しました。複数ウィンドウである必然性がより見えてくると良いと話します。

HIHAHEHO Studioの平山遼さんは、複数ウィンドウを発想したきっかけが「複数のストーリーを同時に読めたら面白いのではないか」と考えたことと伝え、複数ウィンドウによる視覚的な楽しさをゲーム性に結びつけたいと話しました。HIHAHEHO Studioは今後、ストーリーの内容を具体的に決定するとともに、3つのウィンドウを生かした演出やUIを検討していく予定です。
ウィンドウ自体の仕掛け
面談の後半は、複数ウィンドウを生かした演出についてアドバイザーと意見を交わしました。西川さんは「ウィンドウを閉じる」といった操作などでプレーヤーがストーリーに関与できる仕掛けによって、作品のテーマにより迫れる可能性を示唆しました。また、必要に応じてウィンドウを外したり立ち上げ直したりすることで、異なる時間軸を表現できるのではないかとも話します。米光さんからは、例えば「アサ」「ユウ」が「ヨル」を待っている場面で、「ヨル」が2人の方に走って向かっているなど、使われていないウィンドウを活用する工夫などが語られました。mgr allergen0024さんは、アニメーションをさらに充実させながら、ストーリー展開に合わせて、ウィンドウの大きさが変化したり、プレーヤーがウィンドウ自体を操作できたりする仕掛けについても試行したいと話しました。

米光さんからストーリーの参考になる作品が伝えられました。『ロートレック荘殺人事件』(筒井康隆、新潮社、1990年)は、視点の問題とあるテーマが密接に絡んでいる作品。『自閉症裁判』(佐藤幹夫、洋泉社、2005年)は、本人や裁判官、俯瞰する視点のずれが描かれています。
→NEXT STEP
引き続きストーリーの実装とビジュアル面の検討を行い、1章を完成させる

