実験東京は、AIエンジニアの安野貴博さんとデザイナーの山根有紀也さんによるAIアートコレクティブです。東京を実験場と捉え、画像生成AIなどの急速に発展するデジタル技術を用いたメディアアート作品を制作しています。今回採択された企画『別人電話ボックス』は、ディープフェイク技術を用いて5分間だけ別人の顔と声になれる作品。他者になる体験を通して、都市における他者への想像力を生み出し、新たな視点を獲得する体験をつくることを目指しています。初回面談では、作品の試作のデモンストレーションを交えながらアドバイザーと対話し、作品のコンセプトについてあらためて考えていきました。
アドバイザー:戸村朝子(ソニーグループ株式会社 Headquarters 技術戦略部 コンテンツ技術&アライアンスグループ ゼネラルマネージャー)/さやわか(批評家/マンガ原作者)
初回面談:2024年9月27日(金)
他者を纏う先のパンドラの箱
ディープフェイクのポジティブな可能性
これまで、新しい技術をどう使ったら面白いかという発想で活動してきた実験東京の安野貴博さんと山根有紀也さん。今回は、そうした技術先行の考え方から脱却し、現代美術の文脈でのインパクトを与えられるような作品をつくりたいと話します。
『別人電話ボックス』は、2つの電話ボックスに鑑賞者がそれぞれ入り、自分とは違う顔と声になって対話をするというものです。現在は、作品の試作を用いて、顔と声が変わったときにどういう心理的な変化があるかを検証する作品です。山根さんは、「オンラインミーティングでは、案外相手の顔より自分の顔を見ながら喋っていることが多いと感じる。自分の顔を見ながら話すという状況は人類史的に新しい。セルフィーや『盛れる』アプリの普及もあり、自分の顔に対する認識が変わってきているのではないか」と話しました。
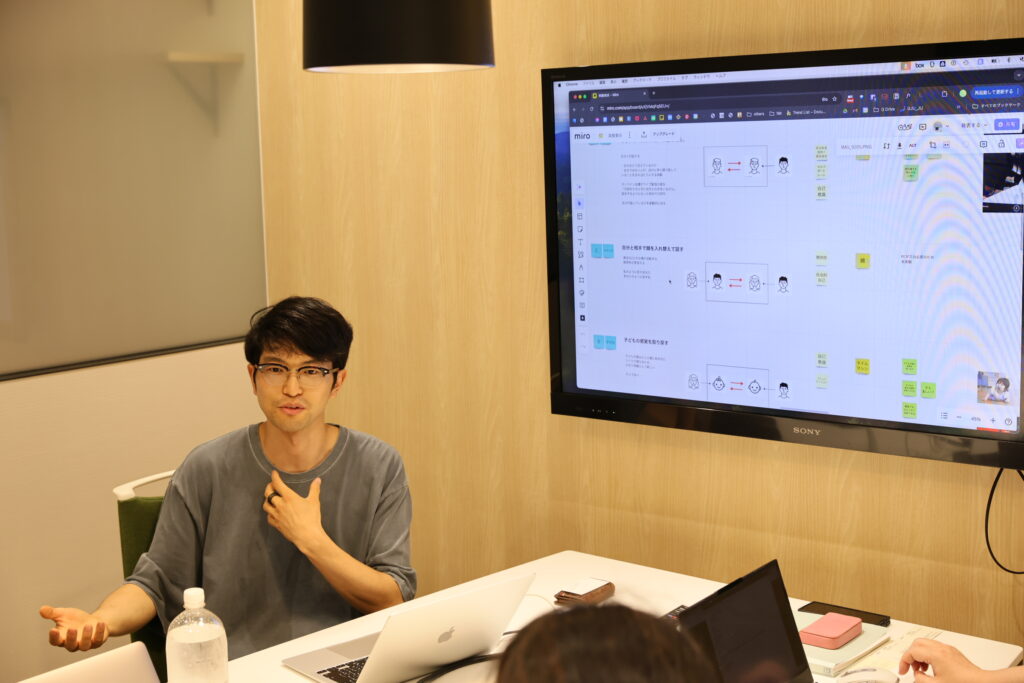
山根さんは、作品の方向性として4つの案を探索していると言います。
1)同じ街に住む外国人や高齢者、小学生など、実在の誰かになる
2)相手が自分になる
3)自分と相手が入れ替わる
4)赤ちゃんなど、過去や未来の自分になる
「いろいろ試すなかで、赤ちゃんの顔を自分に合成すると、幼い頃の感覚に戻ったような強烈な体験を得られた。新しいコミュニケーションが立ち上がりそう」と山根さんは補足します。さらに「赤ちゃんの発達段階では、鏡に映った顔を自分と認識するのが2歳ぐらい。自意識を立ち上げる瞬間を、もう一度つくる作品としての可能性を感じている」と語りました。
今回の作品でディープフェイク技術を使うことについて、安野さんは「ディープフェイク技術は犯罪やなりすましに使われているため規制すべきだという声もある。そうした技術をポジティブに使うことで、技術の規制を慎重に考えたほうが良いというメッセージを出すことができるのでは」と話します。
アドバイザーの戸村朝子さんは、新たな視点から制作したいという2人の考えを受けて、「4つの案に囚われずに、むしろ捨てるくらいの気持ちで実験と検討を続けてほしい」と助言。その上で「4つ目の赤ちゃんの案は、自分の中の何かをアンロックするとも言える発見」と指摘します。

複数の文脈を取り入れていく
戸村さんは、SF小説『老人と宇宙(そら)』(早川書房、2007年)を紹介しました。老人が地球の防衛軍に入隊すると、二度と地球に戻れないかわりに若い体に入れ替わることができるという内容です。「纏うことの意味」という観点が今回のテーマにも重なりそう、と戸村さん。山根さんもそれに同意し、小説に興味を持った様子でした。
アドバイザーのさやわかさんも、戸村さんの一連のアドバイスに同調しながら話します。「自分や作家が違う何かになるという点では、森村泰昌さんが想起される」と指摘し、現代美術の文脈に、ディープフェイク技術の問い直しや価値付けといった文脈を重層的に取り入れることで、作品の深みが出るのではないかと言います。「もともと情報技術は、そこにいない人をいるかのように見せるということでもある」と語るさやわかさん。この作品で、情報技術に対する問いを投げかけられそうであることを示唆しました。

体験を経て発見されるテーマ
面談の後半には、アドバイザーが作品の試作を体験しました。自分の顔と声が赤ちゃんや黒人男性に変わることでどんな心理的変化があるか、意見を交わします。アドバイザーたちも体験のなかで自分のイメージの変容に心理的な影響があったと語ります。さやわかさんは、「見た目からアイデンティティがつくられるということがキーワードになる。人々の思い込みや落とし穴を気付かせるような作品になるのでは」と本企画のもつテーマを確認します。


今後も実験を続けていくと話す実験東京の2人に対し、戸村さんは「人の奥底にあるパンドラの箱は何かを探った上で、作品を通じてどこまでの射程で触るかというところまで考えられるといい」と伝えます。「これは人のアイデンティティに迫り得る作品。それを揺るがすぐらいのものまで試してみては。例えば、自分が小さい時の写真を今の自分に重ねたらどういう気持ちになるか。もしかしたらトラウマや社会的立場がなくなって、自分と対話できるかもしれない」と本企画の秘める可能性を話しました。
→NEXT STEP
試作による実験の継続でコンセプトを深める

