「音を描く」をテーマに、音に反応しリアルタイムに映像が生成されるオーディオビジュアルシステムを制作している阿部和樹さん。『手描きの計算』では、マンガやアニメーションにおける人の手による「描き込み」に着目し、そのプロセスをアルゴリズムで記述することを試みています。最終面談で一気に完成度を高めたアニメーションに、アドバイザーから驚きの声が上がりました。成果発表イベントの後、3月には個展を予定しています。アニメーションや音について、その場でパラメーターを調整しながら議論が交わされ、またギャラリーでの展示という観点からさまざまなアドバイスがありました。
アドバイザー:さやわか(批評家/マンガ原作者)/モンノカヅエ(映像作家/XRクリエイター/TOCHKA)
最終面談:2025年1月21日(火)
人間と機械のインタラクションをどう伝えるか
MIDIキーボードのイメージ
阿部さんからは3月に京橋のギャラリー「art space kimura ASK?」で個展を開催予定であること、またそこでは取り回しの観点からMIDIキーボードを用いることが共有されました。MIDIキーボードを入力に、生成されたアニメーションをプロジェクターで壁面に投影する計画です。加えて、ピアノを弾けない鑑賞者もいることを想定し、あらかじめ短いループ音源を用意。鑑賞者側で音のセレクトや重ね合わせが可能なシステムと音、そして音によって生成されるアニメーションをプレビューしました。

アドバイザーのモンノカヅエさんはアニメーションを絶賛した上で、MIDIキーボードの選択については懸念を示しました。「ストリートピアノなら誰でも触っていいという共通認識があるが、MIDIキーボードだと来場者は触っていいか迷うのでは」と、鑑賞者が触れやすい誘導が必要としました。また、2月の成果発表イベントではMIDIキーボードの代わりにiPadの画面に鍵盤を表示する計画も示されたものの、アドバイザーは再考を促します。「計算機が描くことにどう人間が関わるのか、人間と機械のインタラクションをどう見せるかが本作のコアだと思う。iPadだとその大事な部分が見えにくくなってしまうのでは」とアドバイザーのさやわかさん。鑑賞者がどのようにこの作品を楽しむかを想定し、作品の設計の中に組み込むことが重要といいます。
静止画の展示
個展では作品本体以外にも、アニメーションをキャプチャした静止画の展示を検討していると阿部さん。 さやわかさんは「計算機による作品として見せられたら、このプロジェクトのコンセプトがわかりやすくなる」と賛同。モンノさんからは「紙への印刷ではこのアニメーションの透明感が表現できないのでは。半透明のアクリル板へのUV印刷やiPadでのスライドショーなどを検討するといい」とアドバイスがありました。そのほか、仮設壁の位置やライティング、配線の処理など、ホワイトキューブでの展示で想定されるさまざまな検討事項についてディスカッションがなされました。
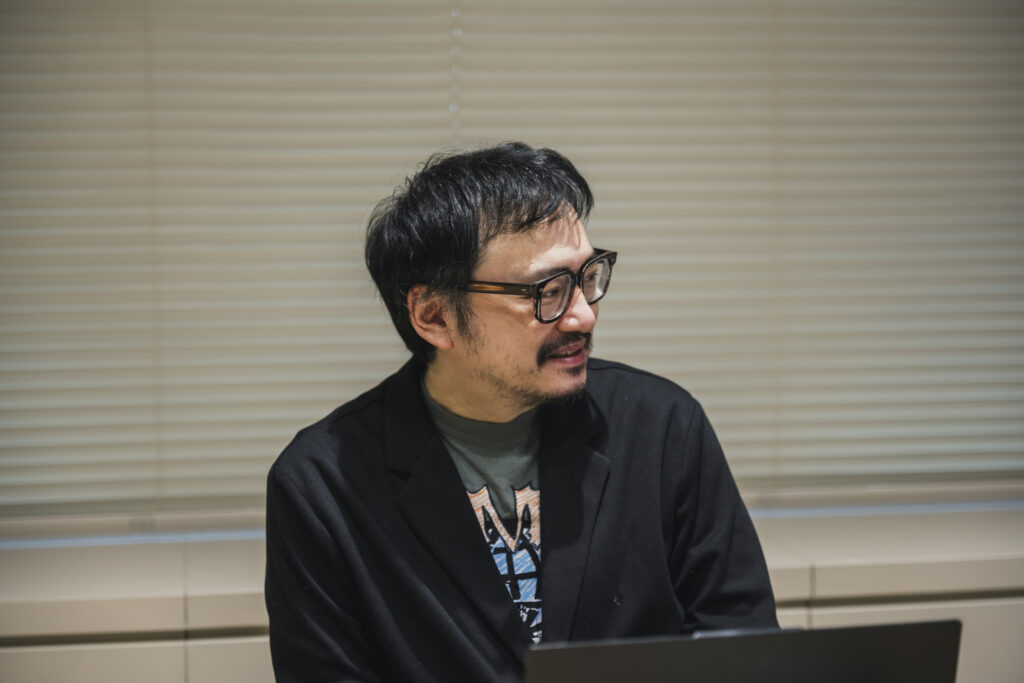
ギャラリー展示ならではの速度感
モニターでのプレビューを観察していたモンノさんから、アニメーションに余韻を求める声がありました。阿部さんにとっても悩みどころだったようで、「何かを残すか、もしくは泡のようにはじける効果をつくるか……ディティールを詰めたいと思っていた」といいます。モンノさんは「板野サーカスと呼ばれる、煙の軌跡をずっと描くようなアニメーションの技法があるが、そのイメージはどうか」と、TVアニメ『全修。』の第2話を見るよう勧めました。「もっと見えてほしいという感じ。何が起きているのか見えたほうが目が気持ちいいはず」とさやわかさんも補足します。
用意する音楽についても、「もっとにゅーんと伸びるような、ゆっくりした音がいいのでは」とモンノさん。さやわかさんからは倍音というキーワードが出され、試しにその場で重ねてみたベースの音が非常にマッチしました。さらに、アニメーションの動きについても「少しスピードを落とした方がいい」とモンノさん。発表の場によって求められる速度感が異なるといいます。「ギャラリーに来る鑑賞者はゆっくり、ぼーっと作品を見たい。動きが早すぎるとすぐに疲れたり酔ったりということもある。ギャラリー展示ならではの速度感を意識するといい」とアドバイスしました。

「絵は完璧なので、あとは音と展示」とモンノさん。たくさんある検討事項に優先順位をつけて取り組むよう励ましました。またストリートピアノを用いた展示については今後も試みてほしいといいます。「オーディオビジュアルのコンペなどに出すときに、ストリートピアノがいいフックになると思っていた。色々な実験をして、フィードバックをもらいながら今後もディベロップしていくといい」と今後の展開に期待を寄せました。
TO BE CONTINUED…
成果発表イベントと3月の個展に向け、音と展示設計を詰める

