ドローイングアニメを中心に、コマ撮りや半立体などさまざまな手法による制作経験を持つアニメーション作家の大髙那由子さん。今回採択された『「記す」アニメーション』は、2人の息子の日々をアニメーションによって「記憶」し「記録」する作品です。子どもたちの行動を記憶から再構築することで、動画や文字には残せなかったものの記録を試みます。成果発表イベントまでに制作するエピソードを絞り込んだ大髙さんは、最終面談でアニメーション制作の進捗を報告。また、アニメーションと併せて展示する予定の「仕掛け絵本」の装置の構想をアドバイザーに伝え、意見を交わしました。
アドバイザー:西川美穂子(東京都現代美術館学芸員)/若見ありさ(アニメーション作家/東京造形大学准教授)
最終面談:2025年1月16日(木)
子どもの空想とアニメーションの自由度の相性
母親(作者)の視点を鑑賞者にどう伝えるか?
前回の面談の後、大髙さんは自身の日記からピックアップした子どもの空想を軸に、3つのストーリーを組み立て、ビデオコンテを作成しました。成果発表イベントまでにこの3つのアニメーションの完成を目指し、制作を進めていきます。最終面談は、ビデオコンテのデモンストレーションと進捗を確認するところからスタートしました。

ビデオコンテを見たあとに大髙さんからストーリーが生まれた経緯の説明を受けたアドバイザーの若見ありささんは、「ストーリーが面白いので、もう少し作品からストーリーが伝わると良い」と話しました。それに対して大髙さんは、鑑賞者にストーリーを伝えるために仕掛け絵本のような装置を用いることを検討していると伝えました。鑑賞者がページをめくりながら、アニメーションと併せて文字でもストーリーを追えるようにする予定です。
アドバイザーの西川美穂子さんは、「空を飛ぶといった子どものユニークな空想が、アニメーションのなかでは逆に当たり前のように見えてしまう」と指摘。「アニメーションで表現することの背景に、子どもを観察している母親、つまり作者の視点もあることをどう鑑賞者に説明するかを考えるべき」と話します。若見さんも、「日記という素材をうまく使うこともできるのでは。子どもの発想と、母親の心境の両方がリンクするとさらにおもしろくなる可能性がある」と続けます。
仕掛け絵本の装置は、プロジェクターを用いたインタラクティブなものにする予定です。装置の大きさや配置、仕掛け絵本のページを自然に開いてもらうための展示方法など、具体的な展示のイメージが話し合われました。
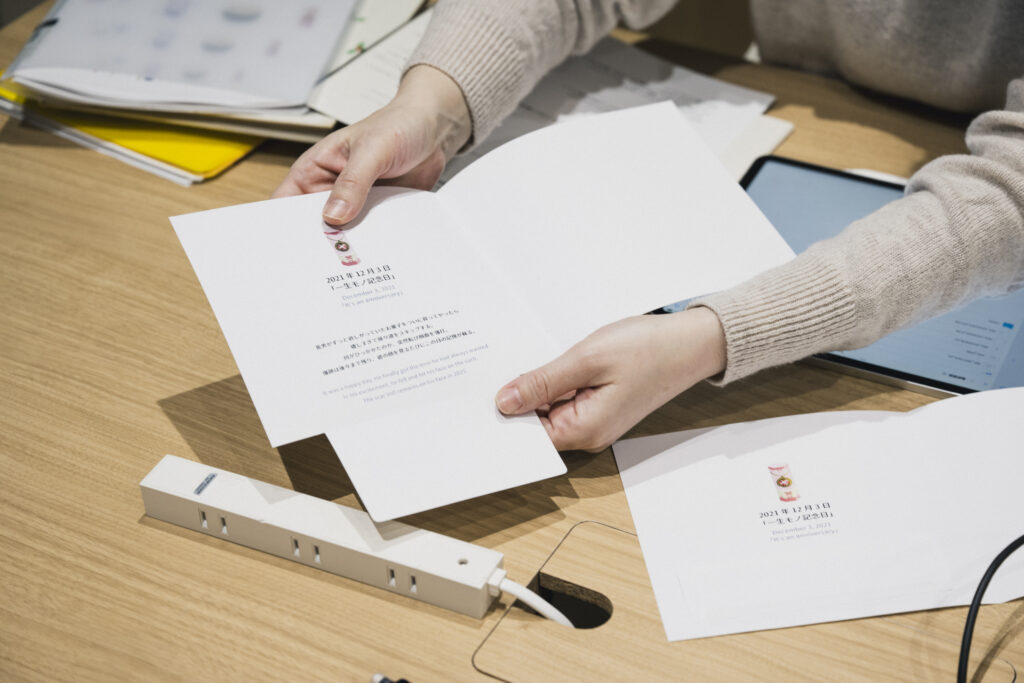

「子どもの記録」というテーマを改めて確認
「制作を進めるなかで子どものキャラクターデザインをどの程度統一するべきか悩んでいる。頭身や髪型を統一した方が鑑賞しやすいと思うが、いろいろな時期のエピソードが混在しているため子どもの姿を統一すると自分の記憶と異なってしまう」と話します。西川さんは、成長を記録するというのもコンセプトのひとつなら頭身に違いがあってもいいのではないかと話しました。若見さんもそれに同調し、「鑑賞者はそれぞれのストーリーを独立したものとして見るので、子どもの姿が変わっても気にならないのでは」と付け加えます。
また、アニメーション表現について若見さんから提案が。子どもが転ぶシーンで子どもをアップにするなど、誇張表現をプラスしても良いのではないかと伝えました。淡々とした雰囲気が大髙さんのアニメーションの持ち味であるものの、「母親目線の観察」というテーマを感じさせるには母親の心が動いた瞬間をもう少し印象的に見せることも検討してみては、と話し大髙さんもそれに同意しました。

作品を仕事にする
今回、アトリエを借りることで制作に集中できたと振り返る大髙さん。今後も本シリーズのアニメーションの制作を続ける予定ですが、さらにその先も制作を続けていくためには作品を仕事につなげていく必要があると考えます。そのためにはどのような方法があるか、アドバイザーの意見を求めました。若見さんは、映画祭やコンペの応募が中心になるだろうと話しながら、絵本の制作やウェブ上での連載も考えられるのではと伝えました。西川さんは、アニメーションだけでなく展示のための装置も制作するという今回の挑戦が大髙さんにとって一つの糧になると話し、「例えば今までのようにクライアントワークを行う場合も、可能性が広がると思う。まずは今回の作品のクオリティを高めていくことが今後の仕事につながるのではないか」と伝えました。

TO BE CONTINUED…
成果発表イベントで展示するアニメーションと仕掛け絵本の装置を制作する

